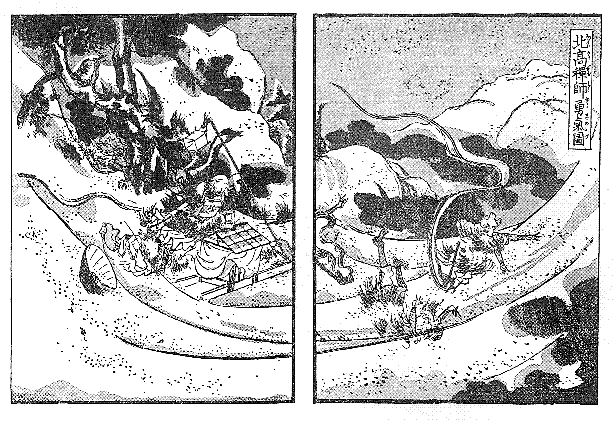
 (P14)
(P14)| 「北高禅師勇気図」 |
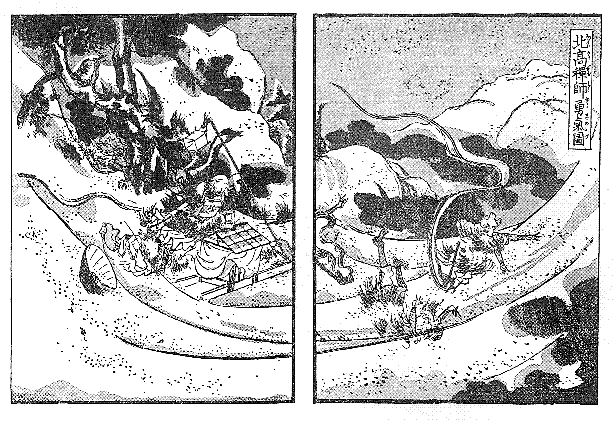
|
| 監修・宮榮二『図説 北越雪譜事典 別冊資料編』角川書店 S57.2.26 より |
 | 上記の参考文献に 収録されていた、 火車のイラスト。 |
 | 『山海経広注』付図(康煕六年刊) 京都大学人文科学研究所蔵 ここではテイと訓んだが、 ある本には「イノコ」と表記している。 |
 道中あふぎの朝風、水無月のはじめ、江戸伝馬町より乗掛仕立て、斉藤徳元といふ人、都にのぼる夏旅、汗水の流るゝ玉川をおもふに、瀑布の袖の色、富士の雪かと心の涼しさ、三保の松陰に夕虹、今も天人の帯なるかと詠め、まだうつの山蔦も青葉にて、秋よりさきに見るもおもしろし。
道中あふぎの朝風、水無月のはじめ、江戸伝馬町より乗掛仕立て、斉藤徳元といふ人、都にのぼる夏旅、汗水の流るゝ玉川をおもふに、瀑布の袖の色、富士の雪かと心の涼しさ、三保の松陰に夕虹、今も天人の帯なるかと詠め、まだうつの山蔦も青葉にて、秋よりさきに見るもおもしろし。 | ※文庫本に記されている著者略歴によると、「鳥山石燕/とりやませきえん 正徳二年(1712年)〜天明八年(1788)、江戸の人。本名は佐野豊房。狩野派の絵師で、妖怪画を好んで描いた。その豊かな想像力で描かれた妖怪たちは、現代にいたるまで妖怪画家たちに大きな影響力を与えてきた。」とある。 |
 <現代語訳>
<現代語訳> 摂州大坂にちかき、平野といふ所に、或る老人夫婦あり。娘二人持てり。皆、外に嫁しけり。
摂州大坂にちかき、平野といふ所に、或る老人夫婦あり。娘二人持てり。皆、外に嫁しけり。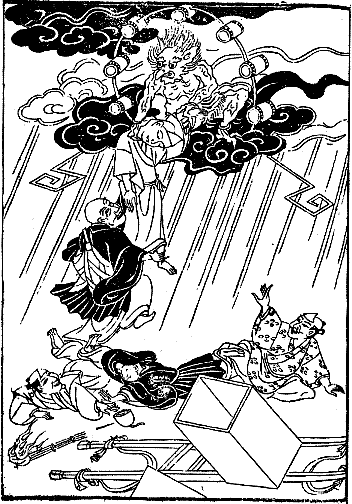 ある人語りていはく、越後の国上田の庄に寺あり。雲東庵と号す。その檀那庄内の人死す。その長老引導をなす。葬礼すでに山頭にいたるとき、電雷はなはだ鳴りて、人頭を割るがごとし。大雨降ること、盆(ほどき)の水を傾くるがごとし。下火(あこ)の松明も消えなんとする時に、黒雲一むら、龕のうへに落ちくだりて、龕の蓋をはねのけて、死人を掴んであがる処を、長老松明をすてて走りかかりて、死人の足にとりつく。なほ引きてあがる。長老手を離さず、固く抱きつきて、共に空にあがる事、一丈ばかり上つて、四、五間横にゆくとき、死人落つるゆへに、長老地に落ちて気を失ふ。諸人抱きたすけ、死人をばとりて、龕にいるるなり。
ある人語りていはく、越後の国上田の庄に寺あり。雲東庵と号す。その檀那庄内の人死す。その長老引導をなす。葬礼すでに山頭にいたるとき、電雷はなはだ鳴りて、人頭を割るがごとし。大雨降ること、盆(ほどき)の水を傾くるがごとし。下火(あこ)の松明も消えなんとする時に、黒雲一むら、龕のうへに落ちくだりて、龕の蓋をはねのけて、死人を掴んであがる処を、長老松明をすてて走りかかりて、死人の足にとりつく。なほ引きてあがる。長老手を離さず、固く抱きつきて、共に空にあがる事、一丈ばかり上つて、四、五間横にゆくとき、死人落つるゆへに、長老地に落ちて気を失ふ。諸人抱きたすけ、死人をばとりて、龕にいるるなり。

