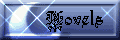「微睡み:小狼編1」
(…痛い…)
李小狼は夢の中ですら苦痛を全身で受け止めていた。
自分が眠っていること、夢を見ていることは薄々わかっていた。
そしてまた、体中の骨という骨が悲鳴を上げているのは夢でもあり、また、現実でもあるということも。
眠っていても、起きていても同じ苦痛から逃れられないのなら、いっそのこと起きてしまいたいと思っているのだが、
身体が意志に抵抗し、薬指はおろか瞼すら動かせないでいる。
(ケルベロスはまだか…)
半ば夢の中にいるというのに、不思議とあたりの様子はよく解る。
木之本が怯えるのもかまわず、ケルベロスが偉を呼びに行ったことも知っている。
二人の会話の一部始終はしっかり聞こえていた。
木之本は自分が眠り込んでいると思っているので余計に怖がっているようだ。
無理もない、と小狼は思う。
ただでさえ闇が深い今の季節の夜の夜中。しかも側にいるのは疲れ果てて眠り込んでいるおれがいるだけだなんて、
心細いのも当然だ。
なにしろ木之本は無類の怖がりなのだから。
その心細さは気配だけでも充分読みとれる。
だから、眠り込んではいけないーという思いがいっそう、小狼に苦痛への抵抗を要求している。
起きあがれないまでも、自分は眠り込んではいないのだから、なにかあっても大丈夫だーという意思表示でもしてやりたい
のだが、できないでいる。
(遅いぞ、ケルベロス!)
せめてケルベロスがいてくれれば、と思うのだがまだ戻ってこない。あいつが行ってからずいぶん時間がたったような気がする
のはおれだけか?
もどかしくて仕方がないのだが、絶え間なくせめよせる痛みの波と疲労に抗うすべはない。
ただじっと背を木に預けて、苦痛がすぎ去るのを待つしかなかった。
そんな彼にとって救いなのは、木之本が泣いたりわめいたりしないこと。怯えながらも大人しくケルベロスの帰りを待っている。
一度叫び声をあげたが、それすらも恐怖故のことではなく、自分とケルベロスの失態に遅ればせながら気づいたことによるものの
ようだった。
今はただ黙って自分の傍らにいる。
確かに木之本がフライを使えばことはずっと簡単だったろう。だが、木之本は行くべきでなかった。
フライを使っても、こんな夜中に木之本を一人で行かせるわけにはいかない。その点、彼はケルベロスに感謝している。
いっそ、ケルベロスと行ってくれても良かったくらいだ、とも思っている。
そうすれば、心細い思いをさせなくてすんだ。
でも、怖いのを我慢しても残ってくれていること、こんな状況に我慢してくれていることに小狼は一瞬、喜びを感じずには
いられなかった。そして、そんな自分に驚きもし、困惑した。
小狼の知る女の子に女というものは、すべからく騒々しいものだった。
訳もなく(と、彼には思えるのだが)笑い、そして泣く。四人の姉たちもそうだ。
苺鈴にいたっては人目も小狼の気持ちもおかまいなしで、いきなり抱きついたりもする。
女ばかりの環境で育った小狼は、彼女らの突然迸る感情にいったい何度、困惑し、呆れたことだろう。
香港でクラスメイトとなった女の子たちもみな、小狼には姉たちや苺鈴とかわらない存在だった。
好悪の感情を抜きにして、彼女らを形容する一番の言葉は「不可解」であった。
でもーと小狼は痛みに負けて薄れてしまいそうになる意識を保とうと、必死で思考を続ける。
むろん母は違う。小狼にとって、母はあくまでも「母親」であり、また、李家の長として威厳そのものの象徴でもあった。
女ーという言葉でひとくくりにしてよいはずのない存在なのだ。
(しかし、木之本に…大道寺は…)
この二人も小狼の知る「女の子」とはかなり違うらしいことに、小狼は気づき始めていた。
多分、生まれて初めて、「他者」というものについて真剣に考え始めた小狼は、自分が苦痛に対してゆっくりと鈍感になっていくのに
まだ気づいてはいなかった。